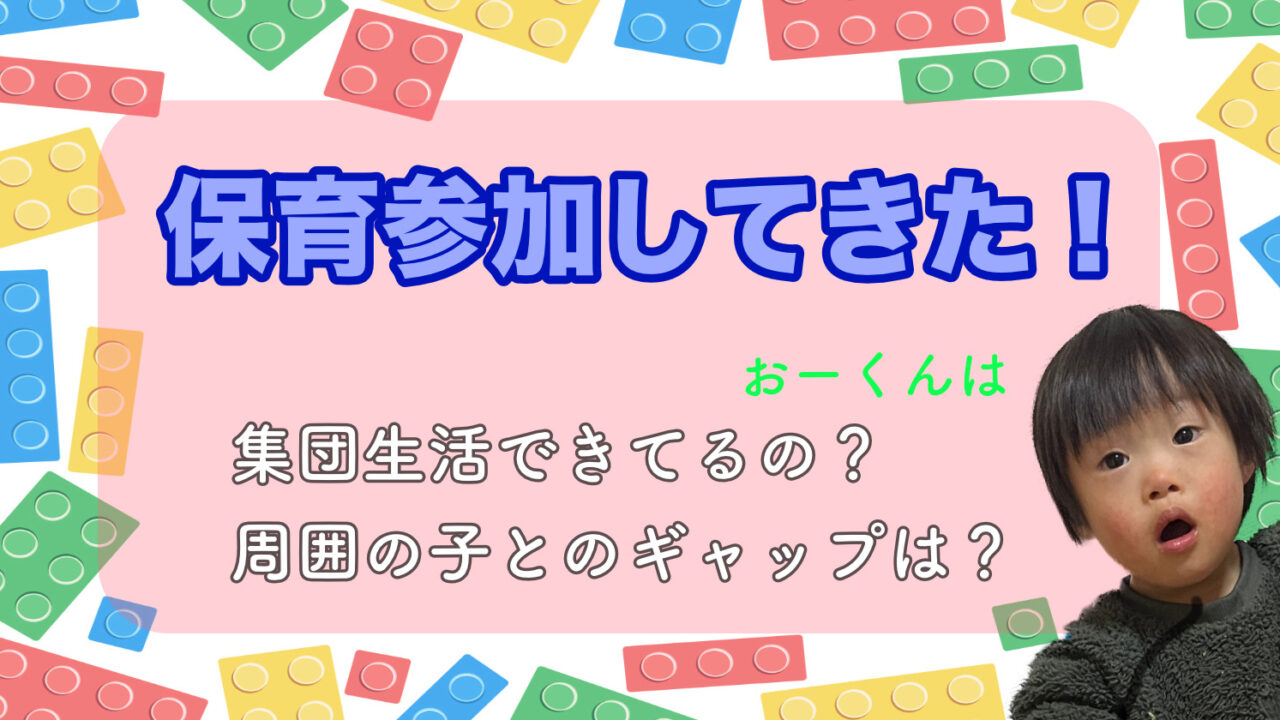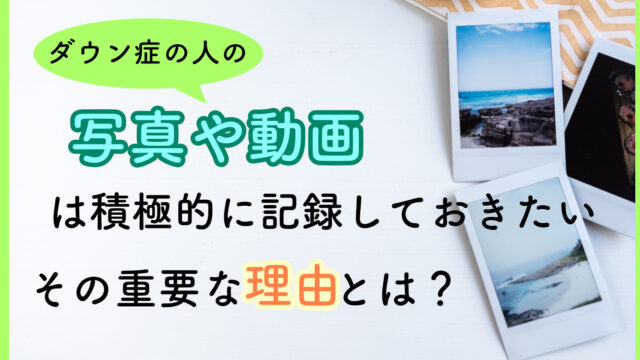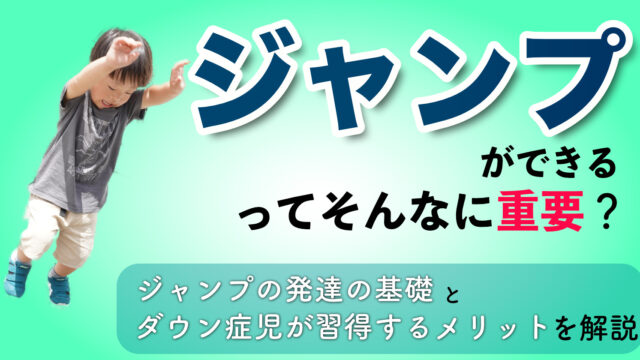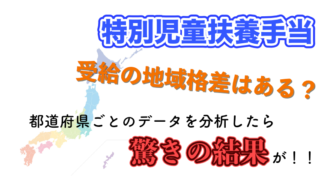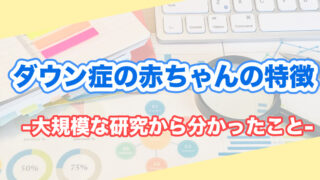ご覧いただきありがとうございます、うこうこです。
先日、おーくんの通う保育園で保育参加があり、父のうこうこが行ってきました。
やはり気になるのは、おーくんがどのように園生活を送っているのか?です。
特に以下の3点については確認したいと思っていました。
①身の回りのことはできているのか?
②集団の活動に参加はできているのか?
③周囲の子との関わりはどのぐらいあるのか?
そして、これらのことを踏まえて4月からの年少さんに上がるための見通しを考えていきます。不安や心配な点があれば、園と話をしていく必要があると思いますので、3つのポイントを意識しながら保育参加に行ってきました!
いざ、保育参加へ!
保育参加の当日、朝、おーくんと一緒に保育園へ登園しました。
その日の内容は、
- 自由遊び
- 園庭で年長さんが体操をしているのをベランダで一緒に行う
- おやつ
- トイレ
- 体操
- 遊戯室で集団遊び(音楽に合わせて走る、揺れ遊び、鬼の的当て等)
という感じで、1時間半ほど一緒に楽しんで遊んできました。
①身の回りのことはできているのか?
これが一番心配でした!
というのも、園の先生による連絡帳の記載では、
“他の子のお手伝いをしたがって、自分のことはあまりやらない”
と書かれていたためです。
家では、「○○持ってきて〜」「△△置いてきて〜」「片付けるよ〜」とかで率先して動いてくれるんですけど、どうしてんなんだろう??大丈夫かなぁ〜。
そんな心配を抱えて行きましたが、その結果、
よくできていました!!
ひとつひとつ指示は必要ですが、置く場所や提出する場所は分かっていました。
その様子を見ていて、おそらくですが、おーくんは自分がやったたときに“褒められたい!”のだと思いました。
僕がいると、できると常にこっちを見て”どう?やったよ!”と伺ってくるのです。そこで、「いいよ!オッケイ!」と応えてあげると、”次やるぞ!”とどんどん準備を進めていました。
普段は、先生に指示されて動いても、先生は他の子を何人も見ているので、”できた!”というときになかなか褒めてもらう機会が少ないのかもしれません。そうすると、先生が対応している子のところに行ったりして、注目を得るために手伝おうとしているのではないだろうか?と考えました。
あくまで仮説ですが、家庭での関わりに活かしていけるポイントなので、ひとつ大きな収穫でした。
また、排泄ですが、みんなでトイレに行く時間に、自分でズボンとオムツを脱いで便器に座っておしっこをしていました!
オムツを脱いでから便座に行くまでもたずに出てしまうことが多かったようですが、少しづつ安定してできるようになってきているようです。
②集団の活動に参加はできているのか?
保育園のような集団生活の場では、みんなでやる遊びや活動にどのぐらい参加できているのか?が重要です。この点を経験してほしくて保育園に通わせていると言っても過言ではありません。
周囲の子と同じようにできる発達段階ではないため、どのぐらい自分だけで参加できていて、逆に、どのくらい先生の補助が必要なのか?を意識して見てきました。
やはり、おーくんは音楽やリズムに合わせて体を動かすのは楽しそうにやっていました!踊りの振り付けも結構覚えていて、びっくりしました。
体を使った遊びは他の子と一緒に楽しそうにやっていたので一安心しました。
ただ、順番がある活動は座って待っていることはできずに、「僕もやるー」と他の子の邪魔になってしまう場面もいくつか見られました。そうすると、先生がおーくんを抱っこしてくれていました。
そして同時に、年少さんになってからの不安も感じました。
今は単純は体を使う遊びが中心ですが、年少さんになるとルールのある遊びをするようになっていくと思います。そうなってくるとおーくんにとってはルールを理解するのがまだまだ難しいので、先生と一緒に参加するか、参加せずに見ているか、他の遊びをしているか、になってしまいます。
こればかりは、年少さんになってからでないと分からないですが、周囲の子の遊びや活動のレベルに次第についていくのが難しくなっていくことは想定していた方が良いと感じました。そして、保育園側と普段の様子を積極的に共有していく姿勢は今後も必要だと感じました。
③周囲の子との関わりはどのぐらいあるのか?
2歳〜3歳の子は”遊び”を通しての関わりが中心です。そのため、周囲のこと遊びを通してどのように関わっているのか?が重要になってきます。
保育参加の様子で感じたことは、
遊びの道具や玩具は同じものを使っていても、遊び自体のレベルが違う
ということでした。見立て遊びやごっこ遊び、ブッロクなどの構成遊びなどイメージを使う遊びを多くしていたり、遊びを通しての関わり方の多くがことばを介してのやりとりが中心だったりと、おーくんにはついていくことが難しいのが現状でした。
発語もないのでやりとりも分かってもらえない。指差して「あー!」と言っても他の子には何を言いたいのか分からないことが多い。よって、あまり周囲の子から関わりを持とうとする機会は少なくなります。そのため、大人の介在がないと一緒に遊ぶのは難しい。
しかしそれでも、ちょっと異質な存在であるおーくんを排除したり、攻撃したり、からかったりしないところが、2〜3歳台の子どもの集団の良さでもあると感じました。
おーくんはおーくんなりに楽しく遊んでいて、それが保証される場であることを改めて実感して、少し安心ししたのも事実です。
その中でも、嬉しかったのは、2人ぐらいの女の子が「おーちゃーん」「かわいいー」と近寄ってきてくれて、「これ貸してあげる」と関わってくれる子がいました。心の中で『ありがとう〜!』と思って見ていました。
まとめ 〜発見や気づきを日常や今後に活かす〜
保育参加の様子から、
『現在の未満児(2〜3歳)クラスでの生活は楽しく活動もできて良さそう』
ということが実感できて、今年度の生活は安心して考えられると思いました。
また、一方で、
『4月からの年少になってからが心配』
とも感じました。
遊びのレベルやコミュニケーションの現状を考慮すると、できれば、専属でなくても良いので加配の先生がついてくれると安心だし、大人の介在があることでおーくんの社会性やコミュニケーション能力は伸びると思いました。
こればかりは園側の事情もあると思いますので、こちらが感じたことを園の方に伝えていきながら、一緒に方向性を模索していきたいと思います。
また、家での関わり方については、イメージを使った遊び(見立て遊び、ごっこ遊び、構成遊び等)を少しずつ取り入れていくことや、身の回りのことについてはできたら声がけ(気づいていることを伝える、褒める等)をして、動機づけや達成感の向上を図っていくことを意識して関わっていきたいと思います。あと、音楽に合わせて体を動かす遊びももっと一緒にできたらと思いました。
そんな感じで、いろいろな発見と気づきがあり、今後の心構えについて考えることができた保育参加でした!