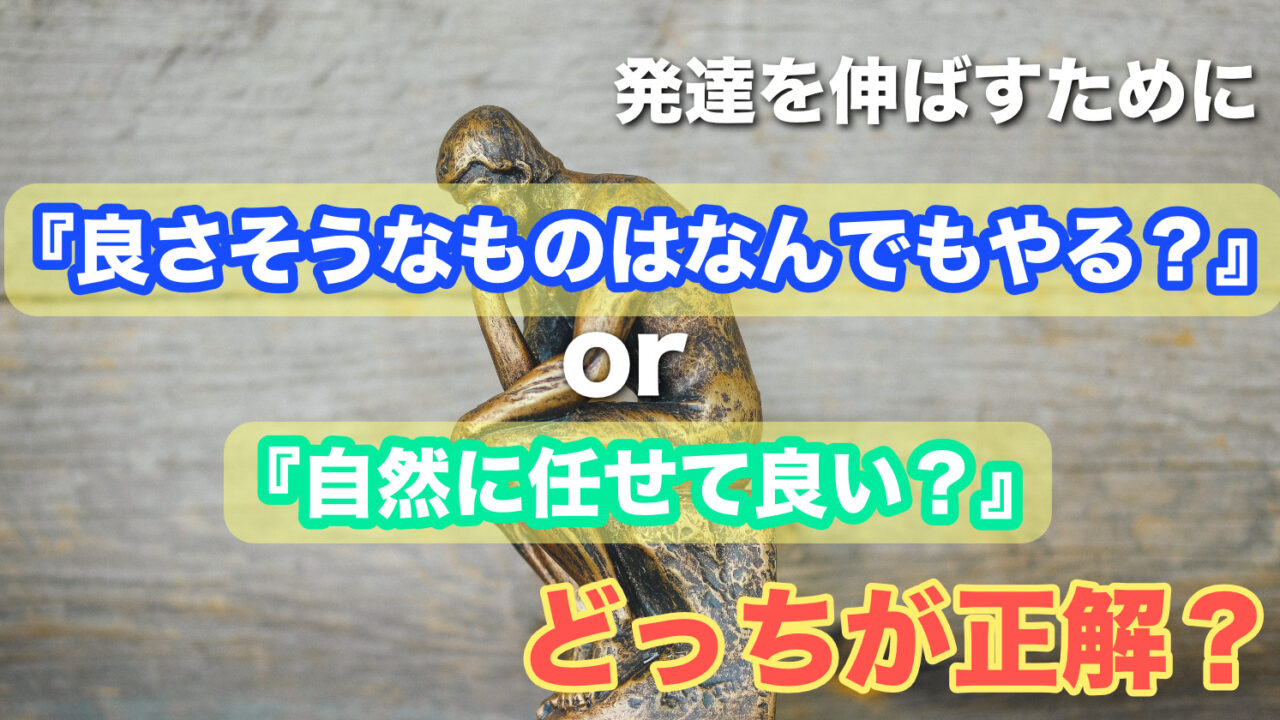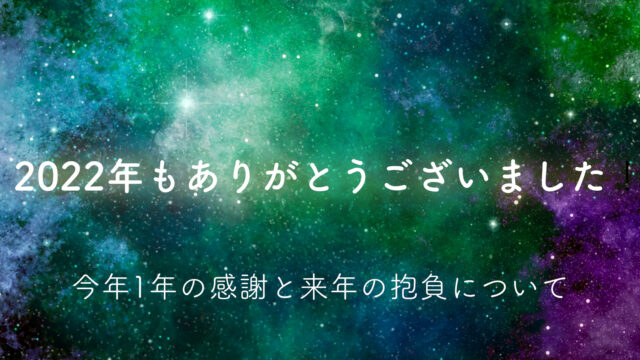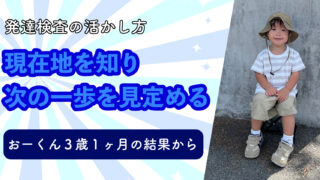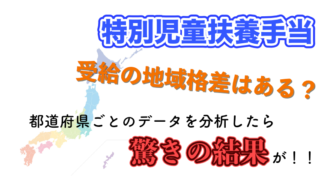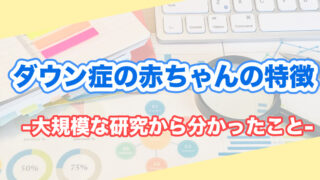ご覧いただきありがとうございます、うこうこです。
障がいのある子どもの子育てをしていると
- 「うちの子はいつ歩くのか?」
- 「いつ話せるようになるのか?」
- 「いつトイレでおしっこができるようになるのか?」
と、発達のひとつひとつが気になることが多いと思います。
そのような悩みに対して、
「大丈夫!成長はゆっくりでもいつかできるようになるから、温かく見守っておけばいいよ」
とアドバイス(『あんまり悩みすぎてはダメよ』の意もあるのでしょう)をされることがあるかもしれません。
しかし、これは間違いです!
じゃあ、
「子どもの発達に良いものは何でもやってみた方が良いのか?」
と考える方もいるかもしれませんが、これも間違いです!
じゃあどうしたらいいんだよ!!
と言われてしまいそうですが、それは、
子どもの今できる一歩先の課題を練習する
がベストな回答です。
それには心理学的に根拠がありますので分かりやすく解説していきます。
おさえておきたい”発達の最近接領域”
発達についての理論はいろいろあるのですが、その中でも有名なのがロシアの心理学者であるヴィゴツキーが提唱した“発達の最近接領域”です。
ヴィゴツキーは、子どもの現在の発達の状態を明らかにした上で、以下の3点について子どもの状態を整理することが重要だと考えました。
- 自分でできること
- 誰かの助けがあってできること
- 誰かの助けがあってもできないこと
ヴィゴツキーは❷の段階を“発達の最近接領域”と名づけ、子どもの発達を促していくためにはこの❷の段階の課題を重視して取り組むことが重要であると考えました。
階段に例えると、一段ずつ登っていけるようにサポートしていくことが発達を伸ばしていくには重要であるということになります。
この考えは現代においても、保育や教育の場面で、子どもの発達や能力を伸ばすために重要な視点として取り入れられています。
例
- 2ピースのパズルは自分の力だけで作ることができる
- 4ピースのパズルは大人の手助けがあると作ることができる
- 6ピースのパズルは大人が手助けしても作ることができない
⇨4ピースのパズルに取り組むことを重視して、さまざまな手助けの手段(形の向きを揃えて渡す、形や色などのつながる部分のヒントを提示する等)を用いて一緒に取り組む。その手助けを少しずつ減らしていき、手助けのいらなくなる❸の段階を目指していく。
「良さそうなものは何でもやる」は間違いではないけれども…
発達の最近接領域にあてはまるのであれば、「良さそうなものは何でもやる」も間違いではありません。
しかし、『助けがあってもできない』❸の領域のものに取り組みすぎるのも良くありません。「できない」を植え付けてしまい逆にやる気や自信を奪ってしまう可能性があります。
発達には順序と方向性があります。一気に階段を数段飛ばして先に行くことはできません。
例えば、数の習得にも順序性があります。『”大きい⇄小さい”』の比較の理解ができていない子に、一生懸命”数”の理解をさせようとしても難しいです。
そのため、その子の現在の位置をきちんと把握して、次の1段(=発達の最近接領域)を登っていくための関わりこそが発達を伸ばすための一番の近道なのです。
障がいのある子にとって”発達の最近接領域”がより重要なワケ
健常の子にとっても、この”発達の再近接領域”は重要ですが、多くの関わる大人はあまり意識していません。それでも、自然と発達していくのは、周囲の子との発達段階にあまり差がなく、周囲の子との関わりが『助け』となっているからです。
“発達の最近接領域”の『助け』には周囲の子との経験も含まれます。周囲の子との遊びや言葉でのやりとりのレベルがその子と同じぐらいであれば、ちょっと上の段階にいる子の影響を受けることが『助け』となって発達を伸ばしていくことができます。
しかし、障がいのある子にとってはどうでしょうか?
障がいのある子は、様々な領域において、周囲の子と発達の差が大きくなりがちです。使う言葉のレベルも、遊びのレベルも、活動の中でできることのレベルも、その差は大きくなってしまいます。そのため、『助けがあるとできる』というよりは『助けがあってもできない』状況が多々生じることになってしまいます。
よって、身近に関わる大人が、子どもの現在の発達段階を理解して、次の一歩を意識した関わりをしてあげることが発達を伸ばすためには必要になってきます。
子どもの現在の発達の段階と次に一歩を知るためには?
“発達の最近接領域”を知るためには、その子の現在の発達の段階と次の段階を知る必要があります。その発達段階を知るための方法は大きく3つあります。
①発達の専門家に聞く
発達の専門性がある専門家や支援者に聞くことが一番だと思います。
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師などがそれに当たります。
医療機関だけでなく、行政や発達支援センターの相談窓口などでも相談できることがあります。
②発達検査を受ける
障がいのある子は、医療機関等で発達検査を受ける機会が多いと思います。
発達検査は現在の発達段階を出すことだけが検査の目的ではありません。
その結果を関わりにどう活かすかが大切です。
検査結果からはその子の『今の発達の段階』が分かりますので、発達についての専門性がある支援者であれば『次の一歩』もわかっているはずです。それを保護者と共有し、その子のは発達に役立てることが発達検査をする本当の目的です。
そのため、結果を聞く際に、「次の一歩として重要なことは何か?」「その獲得のために親ができることは何か?」を聞いてみてください。
書籍で学ぶ
子どもの発達はいろいろな領域があって複雑な点も多々ありますが、一般の人でも分かりやすく解説されている本も多く出版されています。
おーくん父がマジでオススメできる本をいくつか紹介します。
発達全般についてはこの本がオススメです。発達段階に合わせた具体的な遊びが細かく紹介されています。保育士さんは一度は目にしたことがある本だと思います。
運動発達であれば、ダウン症ならこの本一択です。運動の発達段階に沿って何をしたら良いかが全て写真付きで載っています。
オススメな理由については以下の記事を参考にしてください。ダウン症の運動発達はこの本1冊あればOKです!
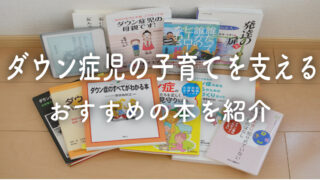
ことばの発達についてはこの本がオススメです。発達段階で何をすれば良いのか分かりやすくまとめられていて、誰でもすぐに取り組めます。
以下の記事でレビューしていますのでそちらも参考にしてください。
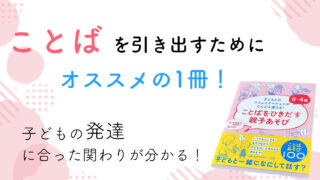
まとめ
『良さそうなものはなんでもやる?』or『自然に任せて良い?』
どちらも正解ではなく、
その子の発達段階を見極め、次の一歩に当たる部分を大人が手助けして取り組む
が、障がいのある子どもの発達を促すには重要です。
ただ、これは多くの子にとって有効な視点でありますが絶対ではありません。
2から3段上の課題もやってみてはいけないということではありません。
ASD(自閉スペクトラム症)の子では、2段や3段を飛び越えて数字や記号、図形の構成などを習得する子もいます。
そのため、基本は1段上を大事にしながら関わることが基本です。
そして、余裕があれば、ちょっと上の段の課題も取り組んでみて、楽しめるなら継続しつつ、やりたがらないなら潔く引くことができれば良いと思います。
何事にも大切なのは、『子どもが楽しく、意欲的に取り組めるか』です。
今回の内容が子どもとの関わりに少しでもお役に立てたら幸いです。