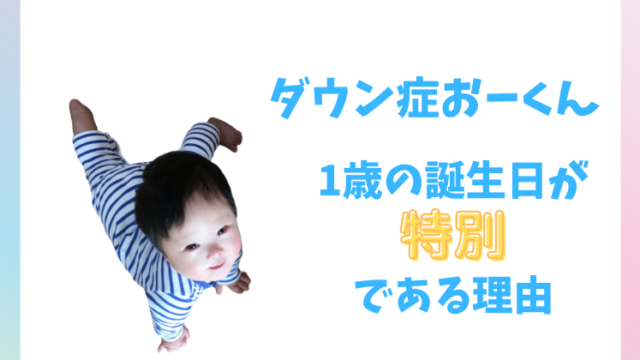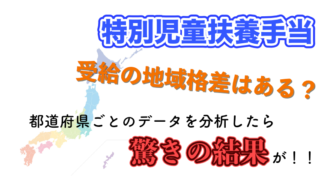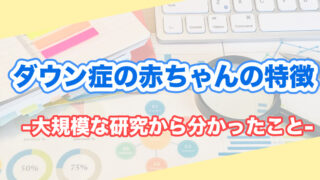ご覧いただきありがとうございます、うこうこです。
ダウン症おーくんですが、
この4月から年長さんになりました!
担任の先生は変わりませんでしたが、加配の先生が変わりました。
何かと気をかけて見てくれている園長先生は変わらず、前の加配の先生も園内にはいらっしゃるので、変化は少なく安心な環境のもとスタートが切れた印象です。
就学先の決断をしなくてはいけない1年
この1年はなんと言っても、就学先の決定が一番の山でしょう。
ダウン症の子をもつ親御さんのほとんどが直面する悩みですよねー
進学先は2択!
多くの方が、
地元小学校進学の特別支援学級(知的障がい)在籍か、
特別支援学校進学か
の2択で悩まれると思います。
うちのおーくんも同様です。
昨年度の年中時には、就学相談を申し込み、園の様子を自治体の担当職員さんに見学していただいたり、特別支援学校の見学も行かせていただいたりしました。
そして、今年度も早速、就学相談を申し込んできました!
今年度はまずは、2回目の特別支援学校の見学と、地元小(主に知障の特別支援学級)の見学をする予定です。
特別支援学校は入学希望の締め切りが11〜12月になることが多いと思います(自治体によります)。入学希望をする場合、就学支援委員会で判定を受ける必要があります。その判定を受けるために提出する書類(園の先生などが作成してくれるので保護者が作成する必要はないです)が、自治体によりますが10月頃に提出することになっています。
つまり、10月までには進学先を決めておく必要があります。
登下校の仕方や放課後の過ごし方を検討する必要がある
進学先を決めていくにあたって、現実的な通学可能性についても考えないといけません。
登下校の手段や時間的余裕について
うちは共働き。近くに祖父母が住んでいるけど仕事をしているので頼れない。
地元小なら距離が近いため、送りは徒歩が難しくても車で可能。特別支援学校ならバス通学になりバス乗り場は近い。しかし時間が不明なので要確認。
放課後の過ごし方について
自宅への帰宅は下校時間に誰もいないので無理。
地元小なら学童利用が選択肢だが、学童職員の人数と質を考えると難しいと予想(姉がかつて利用しており現状把握済み。見守りと注意が主で、必要な”支援”をお願いできる様子ではない。)
地元小と特別支援学校のどちらに進学するとしても放課後デイの利用を検討しないといけない。事業所見学をして受け入れ可能かどうかの相談を進めていく必要あり。送迎のサービスの有無についても要確認。
以上から、うちの場合は、放課後デイの確保と、特別支援学校進学場合のバスの時刻や乗り場の確認が最優先で必要だと考えています。
忘れてはいけない本人要因も要チェック!
おーくん本人の現在の様子について、情報整理も重要です。
現在の発達段階
新版K式の発達検査、田中ビネー知能検査、WPPSI(ウィプシー)かWISC(ウィスク)のウェクスラー式知能検査などの検査結果があると望ましいです。おーくんの場合は定期通院先で実施してもらっている新版K式発達検査の結果を使用する予定です。
社会的能力を見る指標
SM社会生活能力検査、Vineland-Ⅱ適応行動尺度が代表的な検査で、その子の社会せ活に必要な能力や、集団での適応的な行動がどれぐらい取れるのかを数値化して表してくれます。知能は発達段階と、社会生活能力や適応行動能力は別物としてみた方が良いですし、子どもの実態をしっかり把握するには双方の観点は必須だと思います。おーくんの場合は、医療でも自治体でもこの観点による検査は実施してもらえない状況です。
生活の場における実際の様子(行動観察による情報)
保育園や児童発達支援の場での集団参加や他児との関わりの様子、身の回りのことへの対処といった自立行動の様子など、実際の生活の場での行動観察による情報を収集して整理していきます。
客観的な検査結果と、実際の本人の様子を総合的にみていきながら、おーくんん本人のはっったうの様子と特徴について整理していけると良いです。
まとめ
という感じで、
どんな情報を、いつまで確認していく必要があるのか?
その必要な情報をどのように入手していけば良いのか?
につて現時点でのうちのおーくんの様子についてまとめてみました。
おそらく近いうちに今年度1回目の就学相談が行われると思います。その場で、見学の予定の調整や、放課後デイの情報、進学先の決定の期日などを確認しておきたいと思います。
重大な決定がのしかかる1年がスタートしましたが、
焦らずに、時間の許す限りじっくりと、おーくんの将来像を描きながら決めていきたいと思います。