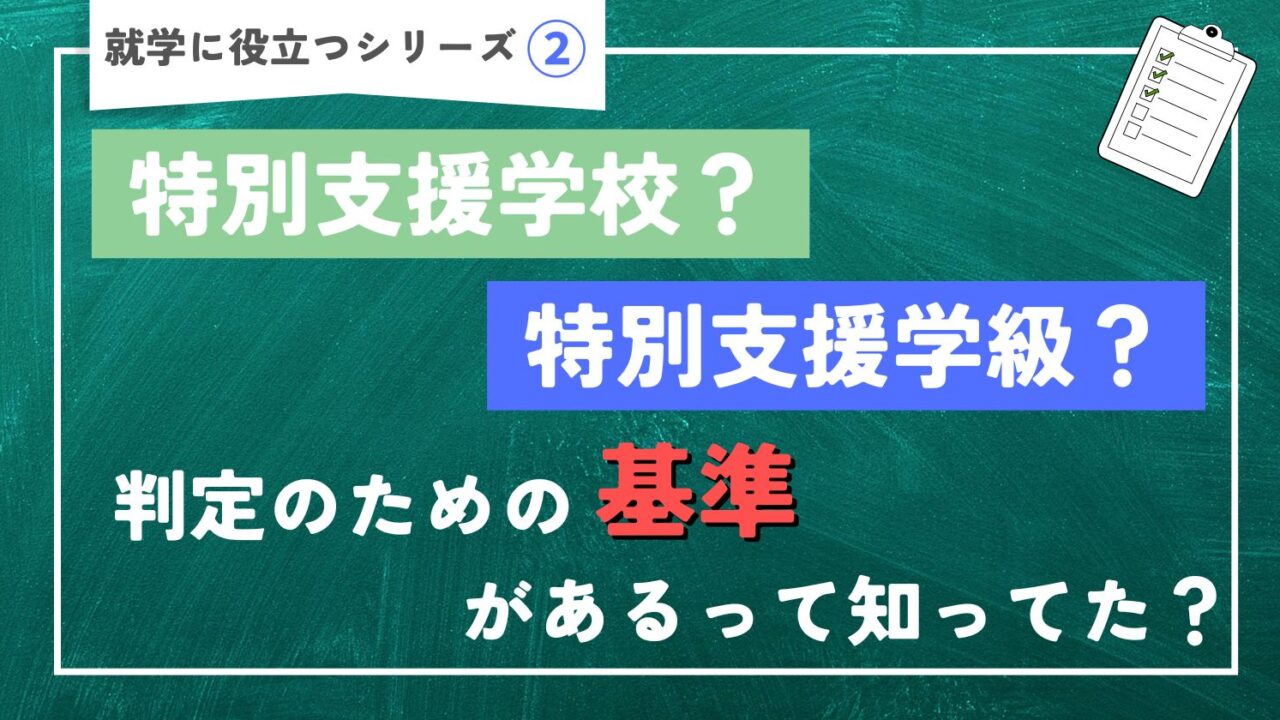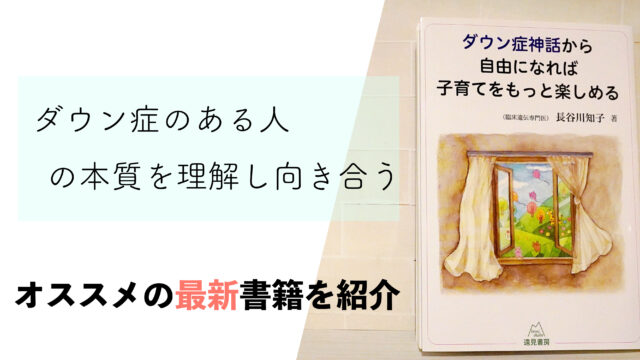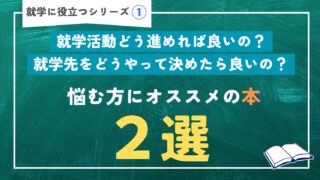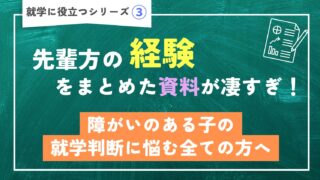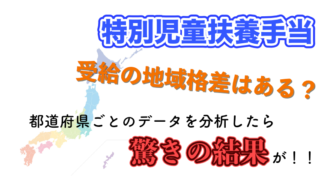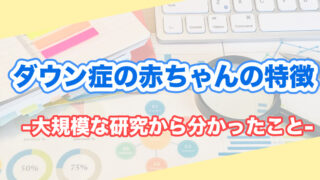ご覧いただきありがとうございます、うこうこです。
ダウン症のある子の多くは知的障がいが併存しています。
そのため、小学校の就学は
地元小学校の特別支援学級か
特別支援学校(養護学校)か
の2択から選択することになると思います。
悩みに悩んで親の意向を就学相談の中で伝えて、自治体の就学判定のための委員会で判定されます。それで通知が来ます。「あなたのお子さんは○○への就学が望ましいです」と。
つまりこれって、判定側に何らかの基準があってもおかしくないと思いませんか?
そうなんです!
知的障がいのある子が支援学校か?支援学級か?を「判定するための基準」というものがあるんです!!
でもこれって親御さんにはあまり知らされません。
でもでも、悩んでいるときには少しでも判断のための情報は欲しいと思われる方は多いと思います。うちもそうでした。
そこで今回は、知的障がいのある子の学びの場を「判定するための基準」ついて解説していきます。
学校教育法22条の3と文部科学省通知
まず押さえておきたいのが、
特別支援学校の対象がどのような状態の子であるか?
を定めた法律があるということです。
それは、“学校教育法施行令第22条の3”と呼ばれるものです。そこでは知的障がいのある子で特別支援学校に通う対象となる子の基準を以下のように定めています。
特別支援学校(知的障がい)の対象となる基準
①知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
②知的発達の遅滞の程度が前号(①)に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
この法律では「特別支援学校の対象となる子の状態」を定めていますが、特別支援学級の利用の対象となる子の基準については文部科学省から出されているいくつかの通知の中で示されています。
特別支援学級(知的障がい)の対象となる基準
①知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要な程度のもの
②知的発達の遅滞の程度が前号(①)に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応の困難がある程度のもの
以上のことから、特別支援学校か特別支援学級か、その境目となるポイントは大きく2つです。
- 他人との意思疎通の困難さの程度 → コミュニケーション能力
- 社会生活への適応の困難さの程度 → 適応行動能力
しかし、難しいのはそれらの能力の『程度』の判断です。
「困難」と「軽度」の違いは?
「著しく困難」と「困難がある程度のもの」の違いは?
あいまいなので分かりにくいですよね。
そこで、この点について解説されている文科省の資料を見ていきたいと思います。
困難さの程度は具体的にどういうものなのか?
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課が出している“教育支援資料”によると
特別支援学校(知的障がい)の対象となる基準
・「他人との意思疎通が困難」とは、特別な配慮なしに、その年齢段階に標準的に要求されるコミュニケーション能力が身についていないため、一般的な会話をする際に話された内容を理解することや自分の意思を伝えることが著しく困難であり、他人とのコミュニケーションに支障がある状態を示す。
・「日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする」とは、一定の動作、行為の意味、目的、必要性を理解できず、その年齢段階に標準的に要求される日常生活上の行為に、ほとんどの場合または常に援助が必要な場合である程度のことをいう。
例えば、同年齢の子供たちが箸を1人で使えるようになっていても、箸を使うことが理解できないために、箸を使った食事の際にはいつも援助が必要である。または排泄の始末をする意味がわからずに、トイレットペーパーを使う際には、ほとんどの場合または常に援助が必要である場合などである。
・「社会生活への適応は著しく困難」とは、例えば、低学年段階では、他人と関わって遊ぶ、自分から他人に働きかける、友達を作る、簡単な決まりを守って行動する、身近な危険を察知し回避する、身近な日常生活における行動(身辺処理など)が特に難しいことなどが考えられる。年齢が高まるにつれても、例えば社会的なルールに沿った行動をしたり、他人と適切に関わりながら生活や仕事をしたり、自己の役割を知り、責任を持って取り組んだりすることが難しいことが考えられ、また、自信を失うなどの理由から潜在的な学習能力を十分に発揮することなどが特に難しい状態も考えられる
特別支援学校での具体的な基準について読んでみると、「コミュニケーションも適応行動も色々自分だけはできず、大人による介助がほとんどの場面で必要になる状態」を示していることが分かります。
次に、知的障がい特別支援学級の具体的な基準は以下のようになっています。
特別支援学級(知的障がい)の対象となる基準
・知的障がい特別支援学級の対象は、その年齢段階に標準的に要求される機能に比較して、他人との日常生活に使われる言葉を活用しての会話はほぼ可能であるが、抽象的な概念を使った会話などになると、その理解が困難な程度のものとなる。例えば日常会話の中で晴れや雨などの天気の状態はわかるようになっても、明日の天気などのように時間の概念が入ると理解できなくなったりすることや、比較的短い文章であっても、全体的な内容を理解し短くまとめて話すことなどが困難だったりすることである。
・また、同時に家庭生活や学校生活におけるその年齢段階に標準的に求められる食事、衣服の着脱、排泄、簡単な片付け、身の回りの道具の活用などにほとんど支障がない程度である。
特別支援学級の利用の対象となる子はまとめると
- 言葉を使った会話が可能であること
- 身辺自立のほとんどが自分でできること
となっています。
つまり、知的な能力が遅れている以外は、周囲の子と一緒に会話や生活ができる程度といえます。
法律の基準があいまいな理由
文部科学省の資料には具体的に子どもの状態について記載してありましたが、あくまで「資料」であり、学校教育法の22条の3が基準としては重要であるといえます。
では、22条の3での基準はあいまいな表現になっているのでしょうか?
それは、
地域全体の教育体制、各学校の支援体制の実情に応じて判定を柔軟に行うため
だと思います。
例えば、ダウン症の子でよくあるのは
言葉は単語程度なら話せて、指示や説明はそれなりに理解できるし、ジェスチャーで意図はそれなりに伝えることができる。身の回りのことの一部は介助が必要だが声がけすれば大t代のことは自分でできる
という子の場合、特別支援学校に行く子もいれば、特別支援学級に行く子もいます。
先ほどの資料の基準で言えば、特別支援学級の対象に当てはまるには少し足りないけど、特別支援学校の基準ほどできないわけでもない
なので、
地域の支援体制(今までの歴史、インクルージョンへの考え方、就学判定委員の質、特別支援学校が果たしている役割など)や
地元小学校の支援体制(支援への意識、特別支援コーディネーターの質、支援学級の数など)によって、判定は変わってきます。
特別支援学級は定員が8名と決まっていますので、それ以上になる場合は学級を増やし担任の先生をつけなくてはいけなくなります。特別支援学校も一応定員があります。
そのような受け入れる側の事情を考慮しながら判定するためにも、あいまいさを残しておく必要があるのです。
まとめ
今回の内容をまとめると以下のようになります。
- 特別支援学校と特別支援学級の利用については法律と文科省の通知により基準が存在している
- その基準は子どもの状態像の大枠を示しながらも、柔軟に判断できるための余地を残した表現になっている。
今回の内容を押さえておくことで、就学相談での話し合いが整理しやすくなるかもしれません。
「発達指数(知能指数)で判断しようとしてくるけど、基準とは違うはず。強引とも思えるし、何か裏があるのか?」と整理できれば一部の検査の数値を重視している理由を聞くことができます。返答次第では今回の内容を持ち出して確認することもできます。
「『言葉でしっかり話せないから支援級では難しい』と言われるけど、法的基準では”意思疎通”との記載で言葉だけでに限らないコミュニケーション全般を示しているはず」と整理できれば、言語発達の専門家(医師、言語聴覚士など)に現在の発達の様子と今後の見通しについて助言をもらい、「言葉は単語レベルですが非言語を含むと意思疎通は概ねできています。今後の発達の見通しとしても発語は増えていくと専門家から評価をいただいています」と伝えることができるかもしれません。
さまざまな背景事情があるため、就学支援担当者と学校側が考える想定もあり、その方向に話を進めていこうとすることもあります。あまりにそれがいきすぎて「教育に子どもを当てはめる」ような形になってしまうこともあります。
しかし大切なのは、
その子にとってよりより学びの場はどこなのか?教育としてできることは何なのか?
を話し合っていくことだと思います。
そのためにも、判定側の都合を知っておくことはとても有用だと思います。
そして、最終的には本人と保護者の意向が尊重されることになっていますので、あくまで基準は基準であって絶対ではないことを念頭に入れて就学相談を進めていけると良いと思います。